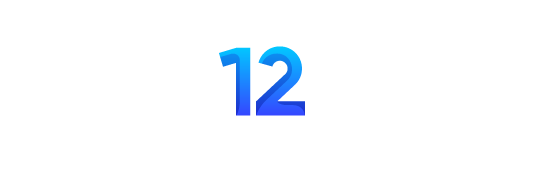「忙しすぎて患者さんとゆっくり話す時間がない…」「カルテ入力や諸々の事務作業に追われて、本来の診療に集中できない…」
こんな悩みを抱える医師は全国に数多くいます。実際、日本の医療現場の最大の課題は「余裕のなさ」と言えるでしょう。特に外来診療では、限られた時間内で多くの患者さんを診察しなければならず、一人あたりの診察時間は平均10分程度とも言われています。この短い時間内で問診、検査結果の確認、診断、処方、説明をすべて行わなければならないのです。
日本医師会医療IT委員会の最新答申「医療DXを適切に推進するための医師会の役割」を読み解くと、こうした問題を解決するヒントが見えてきました。同答申では次のように現状を分析しています。
「日本の医療現場の課題を要約すると、『余裕がない』ということではないだろうか。雑務が多く毎日の業務に、余裕がない。医師の地域偏在・診療科偏在で医療資源に、余裕がない。患者と寄り添う時間を確保する、余裕がない。」(総論 p.2-3)
医療DXを活用した診療効率化は、単なる作業時間の短縮ではなく、「患者と向き合う質の高い時間を生み出す」ことが本当の目的です。今回は、答申から導き出された3つの外来時短テクニックをご紹介します。
①事前情報収集による診察準備の効率化
一般的な診察の流れは「患者来院→受付→問診・情報収集→診察・処方→会計」という順序です。この従来の流れを見直し、「診察前の情報収集」を強化することで診療効率は大きく向上します。
オンライン資格確認等システムを活用した事前情報収集は、特に再診患者の診察準備に有効です。答申では次のような実例が紹介されています。
「地域の総合病院では予約再診患者の保険証確認を毎朝5時に一括照会を実施している。その結果、月平均24,140件の照会のうち、修正が必要となったのは1.8%だった。この一括照会を利用することで、保険証番号の枝番ならびに紹介番号の登録が自動的に実行され、電子処方箋のスムーズな導入が可能となった。」(各論 p.28)
この手法を外来診療に応用すると、次のようなステップで診察準備を効率化できます。
- 翌日の予約患者リストの自動抽出:診察前日に翌日の患者情報を一括で確認
- バイタル測定と問診の分離:看護師による診察前バイタル測定と基本問診の実施
- 診察室レイアウトの最適化:電子カルテ画面と患者の視線を同時に確保できる配置
特に慢性疾患の管理では、この事前準備が大きな効果を発揮します。糖尿病や高血圧などの定期通院患者の場合、前回からの検査値の推移や服薬状況を事前に把握しておくことで、診察時間を有効に使えます。
②テンプレート活用によるカルテ入力の効率化
外来診療で最も時間を取られる作業の一つが電子カルテへの入力です。この負担を軽減するための工夫として、診療科や疾患別のテンプレート活用が挙げられます。
答申では、医療現場のDXについて次のように記されています。
「医療機関等のデジタル化が促進され、業務効率化が進み、効率的な働き方が実現するとともに、システムコストが低減される。ICT機器やAI技術の活用による業務支援や、業務改善・分析ソフトの活用等とそれによる合理化を通じて、医療機関等自身がデジタル化に伴う業務改革を行うことにより、そこで働く医療従事者にとって魅力ある職場が実現。」(各論 p.19)
テンプレート活用には、次のような方法が効果的です。
- 診療科別スタンダードテンプレート:症状や疾患ごとに入力項目を標準化
- 自動テキスト展開機能の活用:頻用する説明文やアドバイスを短縮キーで自動入力
- 音声入力システムの導入:特に診療所では、音声認識技術を活用したカルテ入力の効率化
外来で頻繁に診る疾患に関しては、独自のテンプレートを作成しておくことで入力時間を大幅に短縮できます。例えば、風邪症状の患者には「感冒テンプレート」、腰痛患者には「腰痛テンプレート」というように、症状別にテンプレートを準備しておくと便利です。
また、定型文の活用も効果的です。患者への説明や指導内容、次回の診察予約に関する記載など、繰り返し入力する内容は短縮キーで呼び出せるようにしておくと、数秒で入力が完了します。
③チーム医療による業務分担の最適化
外来診療の効率化には、医師一人の努力だけでなく、医療チーム全体での業務分担の見直しが重要です。答申では次のように述べられています。
「理想的な医療を実現するためには、『社会保障費』、『医療の質』、『医療従事者の負担』の3つの要素を、高いレベルでバランスをとる必要がある。」(総論 p.3)
医療従事者の負担を適切に分散させるための具体的な方法として、次のような取り組みが考えられます。
- メディカルアシスタントの活用:医師の事務作業を専門のスタッフが代行
- 看護師と医師の役割分担の明確化:看護師による問診、説明、患者教育の実施
- 外来診療の時間帯別ゾーニング:新患と再診、緊急と予定の時間的分離
特に注目したいのは「メディカルアシスタント」の導入です。欧米では一般的なこの職種は、医師の指示のもとで診療録の作成や処方箋の準備、検査オーダーの入力などを行います。医師は診断や治療方針の決定に集中し、それ以外の業務をメディカルアシスタントが担当することで、診療効率が大幅に向上します。
日本でもいくつかの医療機関でこの取り組みが始まっており、医師の負担軽減と診療の質向上に効果を上げています。
また、看護師と医師の役割分担も重要です。看護師が初期問診や検査説明、生活指導などを担当し、医師は診断や治療方針の決定に集中するという体制を整えることで、医師の診察時間を有効に使えます。
外来診療の時間管理テクニック
診療時間の管理も重要な要素です。時間配分を工夫することで、余裕を持った診療が可能になります。
- タイムマネジメント手法の導入:診察時間のブロック化と目標時間の設定
- 患者ニーズの事前把握:初診・再診・検査結果説明など目的別の時間配分
- 診療の「見える化」:待ち時間や診察の進行状況を患者に明示
特に有効なのが「診察のブロック化」です。例えば午前中の外来時間を30分ごとのブロックに分け、各ブロックで診る患者数を事前に決めておきます。これにより、一人あたりの診察時間の目安が立ちやすくなります。
また、患者の予約時に「本日の受診目的」を確認しておくことも効果的です。単なる処方箋の更新なのか、新たな症状の相談なのか、検査結果の説明なのかによって、必要な診察時間は大きく異なります。予約時にこれを把握しておけば、時間配分の最適化が可能になります。
余裕ある医療の実現に向けて
答申では、医療DXの最終目標(ゴール)を次のように定義しています。
「医療DXのゴールは、デジタル技術を駆使することによって、国民皆保険と地域医療を守るとともに、より安全で質の高い医療を実現し、医療従事者の負担を軽減して、余裕を持って患者に寄り添うことができるよう医療現場を変革することである。」(総論 p.2)
外来診療の効率化は、単なる「時間短縮」や「患者数増加」が目的ではありません。医師が余裕を持って患者一人ひとりに向き合える環境を作ることが本質的な目標です。そのためには、診察前の準備、診察中の効率化、チーム医療の充実という多角的なアプローチが必要です。
ただし、忘れてはならないのは「誰一人、日本の医療制度から取り残さない」という原則です。
デジタル技術に不慣れな患者さんへの配慮や、医療者側の負担感にも十分な注意を払いながら、段階的に診療効率化を進めていくことが大切です。
医療DXの本質は、単なる「効率化」ではなく「創造性の解放」にあります。デジタル技術によって生まれた「余裕」を患者さんとの対話や医療の質向上にどう活かすかが重要です。専門職としての医師が知的創造性を最大限に発揮できる環境を整えることが、患者一人ひとりに最適な医療を提供する原動力となるのです。
外来診療の効率化に向けた取り組みは、医師一人ひとりの工夫から始まります。ぜひ、今回ご紹介した時短テクニックを参考に、ご自身の診療環境に合わせた工夫を試みてください。患者さんとの対話時間が増え、診療の質が向上する実感が得られるはずです。
(出典:「医療DXを適切に推進するための医師会の役割」日本医師会 医療IT委員会答申、令和6年6月)